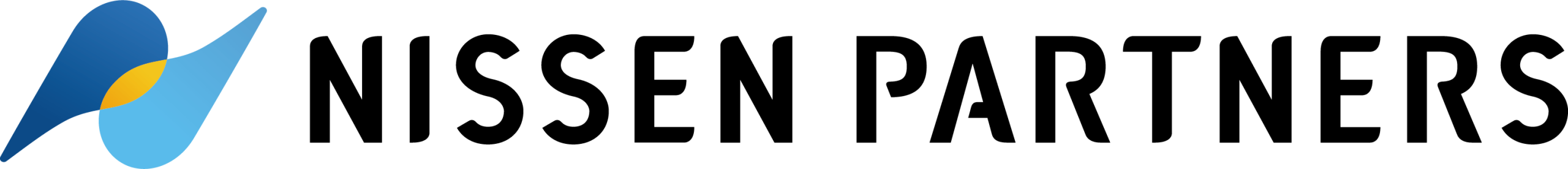地方における製造業の採用が注目される背景
製造業は日本経済を支える重要な産業ですが、近年は人材不足に悩む企業が増えています。特に地方の中小企業では、雇用の確保や若年層の流出が深刻であり、採用活動が思うように進まないケースも少なくありません。こうした背景には、都市部への人口集中やデジタル化の遅れからくる採用広報の弱さなどが影響しています。皆さまの企業でも、地域密着型でありながら新規顧客や働き手の確保が難しくなっていませんか。そこで今、「製造業」「採用」「地方」をキーワードにした、より戦略的な施策への関心が高まっています。
また、地方企業の多くが自社の強みをうまく言語化できず、WEBでの発信が弱いという課題を抱えています。既存の顧客や取引先からの紹介だけに頼りすぎると、新たな市場を開拓する機会を逃してしまう恐れがあります。実際に「製造業 採用 地方」「製造業 地方」「採用 地方」などの検索キーワードから自社の採用サイトへの流入を狙うにも、しっかりとしたサイト制作やSEO対策が欠かせません。デジタルの力を活用して求人とビジネス拡大を同時に図るには、地方企業こそ戦略立案が重要になっています。
さらに、中小企業では人材やノウハウ不足、広告費用の限界などにより、十分な採用活動を行えないことが多いのが現状です。しかし、地方の製造業であってもオンラインを活用することで、新しい人材を全国から募ることは可能です。誰に向けて発信すべきかを再確認し、自社が求める人材や顧客層に刺さる情報をしっかりと伝える必要があります。その第一歩として、自社HPのSEOやSNSを通じたブランディングを強化し、地域だけでなく広域に情報を届ける姿勢が求められています。
「製造業 採用 地方」の現状と最新トレンド
地方の製造業に目を向けると、最低賃金の引き上げや労働条件の改善などが進んでいる一方で、企業が本当に欲しい人材を呼び込めるかどうかは別問題です。例えば、愛知県では製鉄業や輸送用機械器具製造業の特定最低賃金がそれぞれ1,111円と1,081円に改正されることが決定し、令和6年12月16日から適用されます(参考)。山形県も令和6年12月25日から特定産業別最低賃金を引き上げ、現在の955円を上回る約996~1,017円に設定する見込みです(参考)。また、愛媛県では全ての労働者が対象になる最低賃金が956円に引き上げられ、特定最低賃金として船舶製造業や電子部品製造業などにおいて1,038円~1,070円の範囲で改定されています(参考)。
これらの事例からもわかるように、全国的に最低賃金水準は確実に上昇基調にあり、地方企業としては賃金面での競争力を上げる努力が求められています。一方で、地域に根ざす中小企業でも魅力的な就業環境を整えることができれば、都会に出ていく若年層が地元に残るきっかけになる可能性もあります。実際「製造業 採用 地方」という検索をする人の中には、「地元に貢献したい」「自然豊かな地域で働きたい」と考えている層が少なくありません。大切なのは、会社の雰囲気や働き方をしっかり伝え、地域の良さと結びつけることです。
さらに、デジタル施策の活用が進めば、地域求人の拡大だけでなく、外部の人材との連携もしやすくなります。たとえばIndeedやマイナビなどの求人サイトや、Linkedin、WantedlyといったSNS型求人サービスなどのオンライン求人プラットフォームを活用して、地域外の層にも訴求することができます。WEB広告は費用がかかるイメージがあるかもしれませんが、ターゲットを絞ることで、無駄なコストを抑えながら効果的な採用活動を実現できます。デジタルへの不安がある方も、求人施策に詳しい専門家やWEBマーケティング、WEB広告代理店と連携して試験的に取り組むことで、段階的に成果を得る方法も検討してみてはいかがでしょうか。
人手不足と賃金改定のポイント
地方の製造業は、人手不足が深刻化しやすい傾向にあります。背景には、若年世代の都市部への流出や、熟練工の高齢化などが挙げられます。生産工程が多様化する中で、特定の専門技術を持つ人材を確保することは容易ではありません。そこで、労働条件の改善や働き方の柔軟化が鍵になります。
まずは、最低賃金だけでなく特定産業別最低賃金も確認し、自社の給与体系が地域の水準と比較して魅力的かどうかを見直すことが大切です。最低賃金の引き上げは労働者にとって好ましい動きですが、企業としてはコスト増になるケースもあるでしょう。しかし、賃金が地域水準より低いと、人材確保は一層困難になります。そこで、製造業における効率化投資や生産性向上の取り組みが必須になります。厚生労働省は「業務改善助成金」制度を設け、中小企業の生産性向上や最低賃金引き上げを支援しています(参考)。
実際、山形や愛媛など複数の地域が最低賃金を段階的に向上させており、事業者側はコスト運用の見直しを迫られています。事業規模に合わせた設備投資や、DX(デジタルトランスフォーメーション)による作業効率改善が、早期に取り組むべき課題です。これらは特に中小企業にとっては負担が大きく感じられるかもしれませんが、長い目で見れば経営の安定化につながる重要な措置です。
また、会社の文化や職場環境を整える取り組みも欠かせません。働き方改革や労務管理の課題に対応するため、都道府県レベルで無料相談窓口が設置される例もあります(参考)。こうした公的支援を活用して、社員のワークライフバランス改善やキャリアアップ環境を提供することで、長期的な雇用にもつながりやすくなります。
特定技能制度がもたらす効果
日本国内の労働力不足を補う方法として、特定技能外国人材の受け入れが注目されています。特定技能は、製造業や自動車整備業、ビルクリーニング業など特定の業種で認められる在留資格です。中小企業にとっても、この制度を活用することで海外から専門技能を持つ人材を確保できる可能性があります。一定の要件を満たす企業は手続きが簡素化される仕組みもあり、手続きの負担軽減を実感する事業者が増えています(参考)。
ただ、一度特定技能外国人を受け入れるとなると、言語的・文化的障壁への配慮が必要です。経営者や人事担当者が正しい制度理解を持ち、必要に応じて通訳や生活支援などの仕組みを整えることが重要になります。実際、工業製品製造業向けに専門の相談窓口が設置され、多言語対応のサポートが受けられる体制が整備されつつあります(参考)。外国人材にとっても安心して働ける環境がある企業は、その分野でのブランド力を高められる可能性があります。
さらに、特定技能制度を取り入れることで、多様な文化背景を持つ人材が職場に加わり、新しいアイデアの創出や海外取引拡大の足がかりになることもあります。特に地方企業は、地域内において外国との接点が少ない場合が多いだけに、積極的に制度を活用してグローバル思考を育むことが得策です。
労務費の適切な転嫁と地方求人拡大
中小企業が持続的に成長するには、「製造業」「採用」「地方」にフォーカスした戦略立案と同時に、労務費を適正に顧客や取引先に転嫁できる環境づくりが欠かせません。内閣官房と公正取引委員会は、労務費を適切に転嫁するための指針を策定し、サプライチェーン全体で賃上げを支える仕組みを強化しています(参考)。このように発注者と受注者がコミュニケーションを取りつつ、交渉記録を残すことで、公平な取引関係を構築しやすくなります。
また、地方求人の拡大のためには、地域や業界団体、自治体と協力してイベントや就職フェアを開催する方法も挙げられます。地元の高校や専門学校、大学などと連携し、製造業の魅力や企業の成長ストーリーを学生に伝える試みも有効です。実際、北海道経済産業局のように地域産業の活性化をミッションとする組織が拠点ごとに存在し、新しい産業育成や労働環境の向上に取り組んでいます(参考)。こうした取り組みを活用しながら、自社の魅力をアピールしていきましょう。
労務費の転嫁がうまく進めば、適正な価格設定が可能となり、企業としても賃上げの余力が生まれやすくなります。結果として人材確保に役立ち、採用活動がより活性化するという好循環が期待できます。地方企業ならではの強みを打ち出しつつ、業界全体の労働条件が底上げされれば、若年層が「地域で働きたい」と思う流れを作れるでしょう。
効果的な採用活動とデジタル戦略
今後さらに「製造業 採用 地方」の流れを強化するためには、デジタルマーケティングを活用し、募集情報を早く正確に届けることが鍵になります。特にSNSや動画配信サイトなどを使った採用広報は、若者に向けて効果的にアプローチできる手法です。自社サイトを活用する際は「採用サイト」を設置し、採用方法や募集要項をわかりやすくまとめることで、求職者が興味を持ちやすくなります。さらに「地方転職」に関心のある人材層に向けた、オンラインセミナーや相談会を実施するのも手段の一つです。
DX推進には、経済構造実態調査のような統計を活用する視点も重要です。全産業の付加価値や経済構造を把握することで、人材配置や投資計画の見直しを図れます(参考)。地域密着型の企業でも、デジタル施策により広域の顧客を獲得するチャンスをうかがい、従来型の営業だけに依存しない多角的なアプローチを進めましょう。
最後に、読者の皆さまには自社のブランディングを意識することをおすすめします。自社の魅力や価値観を、外部の人材や取引先にわかりやすく発信し続けることで、求人面でも新規顧客開拓でも、大きな効果が得られる可能性が高まります。限られた予算や人的リソースであっても、少しずつ継続して試行錯誤を重ねることで、地方企業でも十分に成果を上げることができます。今のうちから「地方創生」の一翼を担う気持ちで、製造業の採用と地域の活性化を同時に進めてみてはいかがでしょうか。
監修者
小池 正也(こいけ まさや)
Yahoo! JAPANの広告代理店にてWEB広告の運用に携わる。2009年、茨城県での事業立ち上げを機にUターンし、地域に根ざしたWEBマーケティング支援をスタート。これまで300以上の企業や店舗のWEB広告に携わる中で、広告を出すだけでは成果につながらないという課題を実感。
現在はWEBマーケティング全般に携わり、企業の魅力を引き出すWEBサイト制作や、Google広告・Yahoo広告・DSP広告・SNS広告などの運用、Googleアナリティクスを活用したアクセス解析を行う。現場での経験を活かした、改善提案を行っている。
出典
・https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase.html
・https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/tokuteisaitin-20241024.html
・https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
・https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
・https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html