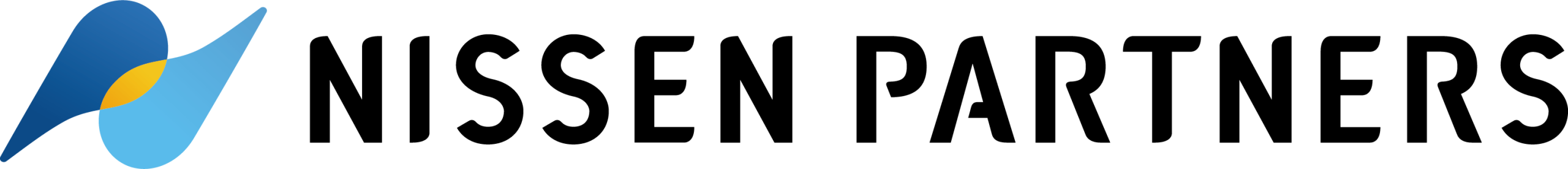製造業の求職者が知っておきたい最新求人動向
製造業での仕事を検討している求職者の方は、まず業界全体のトレンドを把握することが大切です。近年、技術革新が進み、ものづくりの現場における求人が大きく変化しています。特に中小企業では人手不足を解消するために、新卒や中途採用を積極的に進める動きが強まっています。一方、限られた予算で効果を上げるためにデジタル施策を活用する企業も増え、自社の採用サイトやSNS、オンラインの求人メディアを活用した情報発信が重要視されています。こうした取り組みにもかかわらず、若年層へのリーチや専門人材の確保が課題となっており、企業ごとに採用戦略を練る必要があります。
令和6年のハローワーク求人情報が示す製造業の特徴
製造業の最新求人動向を把握するには、ハローワークのデータが欠かせません。令和6年12月の有効求人倍率は1.25倍とほぼ横ばいですが、新規求人倍率や正社員有効求人倍率は前月を上回る結果となっています(参考)。また、同月の産業別動向では、情報通信業や宿泊・飲食サービス業で求人が増加する一方、製造業や運輸業では求人が減少傾向にあります(参考)。
これらのデータは製造業全体の平均値ですが、地方の中小企業でも顧客開拓や後継者不足などを理由に積極採用を進める企業が多く、「製造業 求職者」向けに魅力的な職場環境を整備するケースが増えています。また、デジタル技術を活用して省人化や生産効率向上に取り組む企業もあり、こうした動きを正しく把握することは転職を検討する際にの大きな判断材料になります。
2023年の日本では就業者数が3年連続で増加し、失業率は2.6%と安定した数値を保っていますが(参考)、産業によっては波が大きいのが現実です。企業の成長性や技術力、製品開発力や地域での信頼度が高い企業は、外部環境が変化しても雇用を維持しやすい傾向があります。「製造業 求人情報」を探す際には、安定性に加えて今後の拡張性やスキルアップの機会も重視しましょう。
製造業 採用成功のカギとは?オンライン活用の実際
製造業が採用に苦戦している原因の一つは、人手不足だけではありません。アナログな仕組みや、企業の魅力をうまく伝えられない点も大きな要因です。例えばBtoBの製造業では、ホームページやSNSでの発信が十分でなく、求職者に仕事内容や製品の魅力を伝えきれていない場合があります。そこで重要になるのがオンライン施策です。
最近では、製造業向けの人材サービスを専門に扱う企業も存在し、高度なスクリーニングや仮想現実(VR)を用いた評価方法などが導入されています(参考)。このような革新的な採用手法を部分的に取り入れることで、企業は自社に合った人材を見つけやすくなります。また、採用後の定着率も高まる傾向があり、安定したチーム体制づくりにつながります。
特に中小企業では、費用を抑えつつSNSやオウンドメディアを使った発信を積極的に行う工夫が求められます。魅力的な写真や短い動画を活用することで、「製造業 仕事」のリアルが伝わりやすくなります。応募者は具体的な職場の雰囲気や作業風景を知ることで安心感を得られ、応募へ行動を起こしやすくなります。
中小企業が見逃せない製造業 転職支援と具体策
地方の中小企業は、地元の強みを生かしながらも、都市部と比べると人材確保の競争力で見劣りしがちです。こうした状況を打開するには、専門スキルを持つ即戦力だけでなく、未経験から育成する仕組みや地域ならではの働きやすさをアピールする方策が欠かせません。例えば、職業訓練を活用することで、求職者が実践的な技能を身につけられる環境を提供する取り組みが注目されています。
具体例として、機械オペレータや製缶工・溶接工などを目指す場合、研修機関でスキルを獲得してから転職に挑む方法が一般的です(参考)。また、ものづくりに興味を持つ方へ体験会や見学会を開催するケースもあり、未経験者が実際の作業に触れて自分に合った職種かどうか確認できるメリットがあります(参考)。
企業側としては、人材を求めるだけでなく、定着までのフォロー体制を整えることが求められます。地域密着型企業であれば、地元イベントへの参加やアットホームな職場環境を活かすことで、従業員の満足度とモチベーションを維持しやすいのが強みです。「製造業 求職者」の目線に立ったとき、やりがいと働きやすさの両方があるかどうかが、最終的な入社意欲を高めるポイントとなります。
製造業 求人サイトの選び方と活用ポイント
求職活動を効率化するには、複数のオンライン求人メディアやハローワーク情報を上手に使い分けるのが有効です。大手求人メディアだけでなく、地域密着型の求人メディアや専門メディアに注目することで、ニッチな求人や直接応募が少ない企業を見つけやすくなります。また、検索機能を使いこなし、自分の取得したいスキルや目指す職種で絞り込むのも有効です。 ※日宣パートナーズでは、媒体名のついた求人サイトを求人メディアという名称で統一してサイトと区別しています。
企業側から見ると、求人情報を掲載する際にはスキル要件や勤務体系だけでなく、職場環境や将来性、学べることなどを具体的に書き込むのが効果的です。特に製造業は職種によって仕事内容が多岐にわたり、求職者は「自分にもできるのか、不安はないか」を知りたいものです。写真や動画、あるいは数字で成果目標や研修制度を示すことで、応募意欲を大きく後押しできます。同様に、AIシステムの導入状況や活用事例を伝えることも魅力的な要素です(参考)。
こうした工夫を重ねることで、製造業の魅力を正しく伝えられ、求職者の応募ハードルを下げることが可能になります。求人サイトの一覧性と自社独自の魅力を掛け合わせることが、採用成功のカギといえます。
求職活動から新卒・中途採用まで成功につなげる方法
最後に、製造業界における新卒と中途採用の成功ポイントを整理します。新卒採用では、早期の段階から地元の学校や専門機関と連携し、企業見学やインターンシップを実施することが効果的です。若い人材は現場を知り、実際の声を聞くことでイメージしやすくなり、ものづくりのやりがいや社会的意義を感じられます。さらに、製造業が求める技術的な知識だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力を強化できるプログラムを提供すれば、定着率向上も期待できます。
中途採用においては、即戦力へのリーチと未経験者育成を織り交ぜることが重要です。前述の通り、デジタル技術を用いたオンライン面接や評価システムを導入すれば、候補者のスキルや適性をより正確に可視化しやすくなります。特に高度なロボット工学や品質管理のスキルが要求される企業では、個別対応によって企業と人材のミスマッチを減らすことが可能です。こうしたシステムを活用し、85%以上の成功率を上げる事例も見られます(参考)。
「製造業 転職」「製造業 仕事」を探す求職者は、まずリーズナブルなオンラインツールや求人メディアで企業情報の発信に触れつつ、必要なスキルを得るための訓練機会をチェックすることが大切です。企業側は、従来の紹介や営業だけに頼らず、最新のWebマーケティング手法と併用して幅広い層にアプローチしていくことで、年間を通じた安定採用につなげられます。お互いが視野を広く持ち、適切な情報発信とスキルアップの場を整えることで、限られた予算や時間のなかでも大きな成果を得られるでしょう。
監修者
小池 正也(こいけ まさや)
Yahoo! JAPANの広告代理店にてWEB広告の運用に携わる。2009年、茨城県での事業立ち上げを機にUターンし、地域に根ざしたWEBマーケティング支援をスタート。これまで300以上の企業や店舗のWEB広告に携わる中で、広告を出すだけでは成果につながらないという課題を実感。
現在はWEBマーケティング全般に携わり、企業の魅力を引き出すWEBサイト制作や、Google広告・Yahoo広告・DSP広告・SNS広告などの運用、Googleアナリティクスを活用したアクセス解析を行う。現場での経験を活かした、改善提案を行っている。
出典
・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49776.html
・https://www.jilaf.or.jp/en/news/20240227-3715/
・https://www3.jeed.go.jp/shiga/poly/kyushoku/copy_of_ability_info.html
・https://www3.jeed.go.jp/shiga/poly/
・https://www.apc.jeed.go.jp/zaishoku/2025/V0561.html
・https://gws.sandbox.iam.s.uw.edu/forge-industrial-staffing-livonia-mi