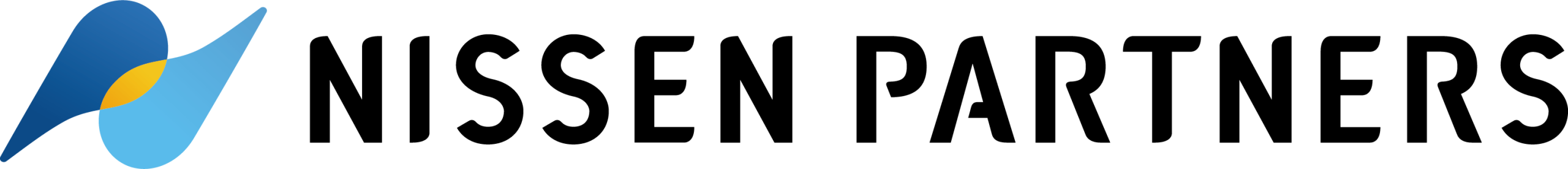地方企業の採用ブランディングの重要性
地方の中小企業にとって、新規顧客や人材の獲得は常に課題となっています。限られた予算や人材リソースの中で、どのように採用活動を強化し、自社のブランド力を高め、地域に根ざした経営を展開していくのでしょうか。鍵になるのが「採用」「ブランディング」「地方」を一体化させた戦略です。
地方企業が強調すべきは、地域密着型の魅力を正しく発信し、そこで働くメリットを求職者や消費者に伝えることです。例えば、地元ならではの暮らしやすさ、安定した雇用、アットホームな風土などを採用ブランディングでアピールする企業も増えています。
一方で、地方には独自の産業や工芸品、特色ある自然や観光資源が多く存在しますが、それらを活かしたブランディングがうまくいかないケースも少なくありません。そこにはデジタル活用の知識不足やインターネット上での露出の少なさなどが影響しています。限られた人材と広告費という制約の中で、戦略的にWebマーケティングを行わなければ埋もれてしまう恐れがあります。
しかし、地方の価値を伝える取り組みは年々広がっています。たとえば、2024年に東京で開催された地方創生や地域活性化をテーマとしたイベントでは、地域活性化に興味を持つ学生と地方創生を目指す企業が交流し、新卒採用やインターン選考のきっかけを生み出しています(参考)。このように“地方で働く・暮らす魅力”をしっかり届ける場を活かすことで、採用パイプを太くし、採用ブランドの認知度を高めることができます。地方企業は今こそ「採用」と「ブランディング」を積極的に結びつけ、地域ならではのメリットを発信する必要があると考えられます。
地方企業が押さえるべき採用戦略
限られた予算やリソースで最大限の効果を上げるためには、採用戦略の準備段階から狙いを定める必要があります。特に地域性を強く打ち出す場合は、採用活動全体で地方企業としての強みを徹底的に言語化し、それを発信するメッセージに落とし込むことが重要です。例えば、地元での認知度が高い企業でも、若年層へのアプローチに苦戦しているケースがあります。その場合は、SNSや採用サイトなどのデジタルを活用しながら、地元の魅力や自社の成長性を訴求することが効果的です。
地域ブランディング事業を通じて自治体や地元企業と協力し、魅力づくりや活性化に取り組むことで地域そのものの価値を高める企業もあります(参考)。地域と企業が一体となる施策は、顧客獲得だけでなく、採用面でも強力な差別化要素となるでしょう。地方企業が自社単独で頑張るだけでなく、自治体や周辺企業と共同でイベントやプロジェクトを実施できれば、若年層の関心を集めやすくなります。
さらに、採用戦略を計画する際には、自社の現状に合った採用方法や採用プロセスを組み立てましょう。採用担当者が1人しかいない、または兼任しているケースも多いですが、その分、外注やツールの利用を検討すれば、採用コストを抑えつつ効率を高められます。実績あるツールやサービスを導入し、採用面接の準備や応募者とのコミュニケーションを自動化するだけでも大きな効果が見込めます。特に採用市場が活発化する時期には、備えた体制で臨むことが必要です。
ブランディング効果を高める方法
ブランディングとは、企業や製品が持つ独自の価値を明確に打ち出し、ターゲットに認知・共感してもらうための活動です。地域に密着した企業ほど、地元の文化や特性をブランドに取込みやすく、ストーリー性のあるブランディングを構築できます。例えば、長年続く家族経営で培った地元住民からの信頼の厚さや、地元の特産品を活用した製造業の技術力など、都市部にはない魅力を前面に押し出すことで、若い求職者にもアピールしやすくなるはずです。
しかし、その魅力が正しく伝わらなければ、人材や顧客を逃してしまいます。そこで活用したいのがデジタルマーケティングやSNS、さらには採用ツールとブランディング手法を組み合わせた発信です。「地方創生テレワーク推進運動」では、企業がサテライトオフィスを地方に設置することで雇用創出や人口流入が見込めるとされています(参考)。このように、働き方の多様化を取り入れたブランディング施策を打ち出せば、新しい働き方を求める人たちの共感も得やすいです。
もう一つ注目すべきは、事例の共有です。例えば、「大手企業からNPOへの転職ストーリー」では、社会課題へのコミットややりがいを志望動機として明確に示すことで、組織の価値観に共感する人材を獲得しています(参考)。地方企業でも、社会とのつながりや地域課題への貢献を強みとしてブランディングを図れば、単なる仕事探しではなく、地方を盛り上げたいという熱意を持った求職者とのマッチングが期待できます。これこそがブランディング効果を高める大きなポイントと言えます。
採用活動のポイント~デジタル活用と採用ツール
採用活動を効率的に進めるには、デジタルプラットフォームと採用管理ツールの導入が不可欠です。応募者情報の一元管理や日程調整、オンライン面接などを活用することで、少人数体制でもスムーズな採用活動が実現できます。
ただ、導入の際は、セキュリティ面への配慮も大切です。海外では不正アクセスを防ぐために厳格な情報管理体制を整えている例もありますが、日本の地方企業においても、応募者情報の保護や運用ルールの明確化は避けて通れない課題です。
中小企業では、初期費用をためらう企業も多いですが、中長期的効果を考えれば十分に検討にあたいします。採用ツールによっては、応募者との日程調整や動画面接、SNSとの連携などがスムーズに行え、地方企業が広域の求職者を取り込む際に大きな助けとなります。オフラインの採用面接だけに頼らず、オンラインで全国の候補者とやり取りできる点は、地方活性化の鍵とも言えます。
さらに、採用プロセスの効率化や効果的なデジタル広告運用をするために、専門家の支援や外部コンサルタントの活用を検討するのも一策です。自社の強みをどうアピールするか、データをどのように分析して採用課題を解決するか、など多角的な視点が求められます。そこで重要なのがブランディング戦略と連携した採用活動です。会社の世界観や価値を示すブランディングが定まれば、それを採用サイトやSNSへ展開しやすくなり、広告を含めた採用計画を一貫性のあるものに仕上げられるでしょう。
地方創生・地方活性化のための採用ブランドづくり
地方創生や地方活性化を掲げる企業こそ、採用ブランドを高める必要があります。採用ブランドとは、求職者が「この会社で働いてみたい」と思う要素を明確に打ち出すことであり、単純な待遇条件だけでなく、魅力的な職場環境や社会的意義もしっかり伝えることが重要です。最近は地方移住やワーケーションなど、多様な働き方に注目が集まっています。こうしたトレンドを上手に取り込み、地方求人を促進できれば、地域の雇用創出や人口減少の緩和につながる可能性があります。
また、地域企業を支援する外部の“伴走者”の存在も見逃せません。マーケティングやコミュニケーションの専門家として教育機関などで活動しながら、地域企業のコンサルティングを行う人材も増えています。地方企業が抱えるブランド構築の課題を外部視点で補うこうした存在は、採用計画やブランディング施策をスムーズに進めるうえで大きな助けとなります。
さらに、海外でも入学者募集や採用活動にデータ分析やデジタル戦略を積極的に活用する取り組みが進んでいます。大学がSNSやメールマーケティングを駆使して応募者との接点を最大化している事例などは、規模こそ異なるものの「データに基づいた発信や複数チャネルを組み合わせた広報」という観点で地方企業にも参考になる点があります。
地方企業が描く未来~課題から成功へ
地方企業が採用とブランディングを両立させることは、単なる人材確保の手段ではなく、将来的な地域経済の発展にもつながります。
データを駆使してターゲットやメッセージを最適化する取り組みが進めば、限られた広告費でも着実に成果を上げることが可能です。海外でもこうした流れは加速していますが、地方企業も自社に合った形で少しずつ取り入れていくことが求められます。
とはいえ、地方企業にはデジタル人材やWEBノウハウが足りない、担当者が兼任で忙しいなどの厳しい現実があります。しかし、だからこそ外部の知識活用やツール導入、さらには補助金や自治体との連携が効果的な打ち手になります。専門家との協働やインターン受け入れプログラムを通じて、若年層を取り込む地ならしを進めるケースも増えています。そして何より、自信を持って企業の魅力を伝えられる社内体制、つまり自社の強みを言語化し共有するステップが必要です。その後に採用市場向けのアピールを行えば、より多くの関心を得られるでしょう。
採用担当者の負担を軽減しつつ、採用成功やブランディング強化を実現するために、まずは社内外のリソースを洗い出すことから始めてはいかがでしょうか。そして、これまで実施してこなかったデジタル施策や新しい働き方への取り組みも検討することで、地方経済を活性化させる新しい担い手を呼び込める可能性が広がります。今後、地方企業がさらなる発展を遂げ、地域の雇用や人口維持が実現できるかどうかは、採用・ブランディング・地方を一体と捉え、新しい手法や多様な人材を活用できるかにかかっていると考えられます。
監修者
小池 正也(こいけ まさや)
Yahoo! JAPANの広告代理店にてWEB広告の運用に携わる。2009年、茨城県での事業立ち上げを機にUターンし、地域に根ざしたWEBマーケティング支援をスタート。これまで300以上の企業や店舗のWEB広告に携わる中で、広告を出すだけでは成果につながらないという課題を実感。
現在はWEBマーケティング全般に携わり、企業の魅力を引き出すWEBサイト制作や、Google広告・Yahoo広告・DSP広告・SNS広告などの運用、Googleアナリティクスを活用したアクセス解析を行う。現場での経験を活かした、改善提案を行っている。
出典
- https://netsui.or.jp/20240802_careerfes/
- https://www.cgc-shiga.or.jp/use/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE
- https://www.chisou.go.jp/chitele/sengen/index.html
- https://www.katariba.or.jp/magazine/article/interview230922/
- https://www.jobs.virginia.gov/
- https://music.utk.edu/people/alissa-galyon/
- https://jobs.fdu.edu/postings/10476
- https://www.arcadia.edu/faculty-and-staff/colleen-daley/