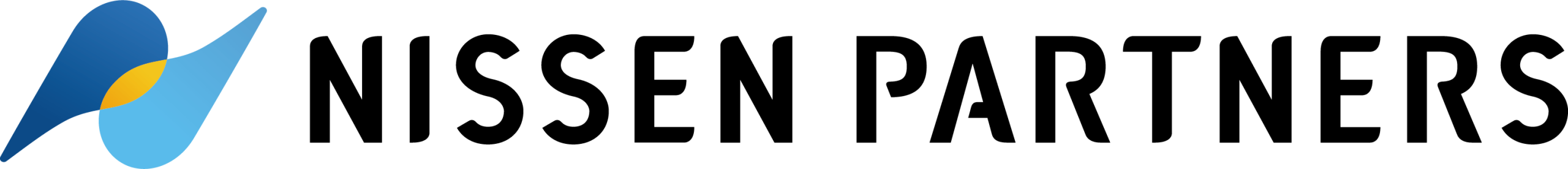はじめに
「人を惹きつける」とは、言葉を通じて読者や顧客に強い関心や共感を抱いてもらうことを指します。特に商品やサービスの印象を形づくるキャッチコピーは、その役割を担う大きな要素です。ぱっと見ただけで、その企業やブランドが伝えたい価値や魅力を理解してもらうためには、短くても心に響く言葉選びが求められます
キャッチコピーは単に商品名や特徴を述べるだけではなく、相手が抱えている悩みや理想に寄り添う工夫が必要です。たとえば新しい商品をアピールするときに、専門用語や長い文章を多用すると読み手が疲れやすくなり、本来の魅力を十分に伝えきれない恐れがあります。短いフレーズの中でも、ターゲットが抱く不安や期待の感情をくみ取り、理解しやすい言葉に置き換えることが「人を惹きつける」ための最初のステップです。
今回の記事では、具体的な作成手順やコツを取り上げ、中小企業の方でも実践しやすいキャッチコピー作成の考え方を共有します。
中小企業におけるキャッチコピーの重要性
中小企業の場合、大規模な広告に多額の予算を投じることは難しいケースが多くあります。そのため、費用を抑えつつも効果的なキャッチコピーを考え、戦略的に活用することがポイントです。限られたリソースの中でも、少しの工夫で大きな効果を生むことが可能です。
近年では、インターネット広告やSNSなど、少ない文字数で要点をまとめなければならない場面が増えています。小規模の店舗や個人事業でも、ホームページやSNSの投稿を通じて情報を発信するのが一般的です。その際には、どのように目を引き、興味を持ってもらうかを考えることが重要です。短い言葉の中でインパクトと分かりやすさを両立させる視点は、大手企業同様、中小企業にとっても強力な武器になります。
キャッチコピー作成の基礎
キャッチコピーを考える上で最初に大切なのは、誰をターゲットにしているかを明確にすることです。個人や企業か、どのような年代や性別か、どんな悩みや課題を抱えているのかを具体的にイメージすると、言葉選びの方向性がよりはっきりと見えてきます。たとえば若い世代を狙うなら、親しみやすくてテンポの良い表現を、ビジネスパーソンが主体であれば、信頼感や専門性を伝える言葉を意識します。初期段階で選ぶ言葉の方向性を決めておくことで、最終的なアウトプットがブレずにまとまります。
キャッチコピーは長文ではなく、短くても伝えたい内容を明確に示すことが重要です。読み手がすぐに理解できるよう、シンプルで具体的な表現を心がけましょう。
シンプルで具体的に伝える
情報を詰め込むよりも、一番伝えたい内容に絞ったほうが、「人を惹きつける」インパクトを出しやすくなります。数字や具体的な成果、ターゲットが反応しやすい感情を刺激する言葉を選択して、端的に魅力を示すことが効果的です。たとえば「3分で味が変わる」「リピート率92%」のように具体的な数字を添えることで、説得力が高まります。
また、問いかけ形式を用いると、読み手は答えを想像しながら自然に関心を持つようになります。SNS広告分析でも、疑問文を使ったタイトルはクリック率が高い傾向があります。
さらに、読者に直接呼びかけたり、意外性のある言葉でギャップを作ったりするのも有効です。たとえば「なぜ、〇〇なのに売れるのか?」という構成は、続きを知りたくなる心理を誘発します。
「従来の洗剤より30%短時間で汚れ落ち」といった具体的なベネフィットを示すコピーも、手に取りやすさを後押しします。
キャッチコピー作成のテクニックを活かす際には、あらかじめ何を重視するかを決めたうえで、ターゲットの感情に訴えかけるように組み立てることが大切です。中小企業がオリジナルの雑貨を販売する場合なら、製品のこだわりを数字や結果に置き換えたり、自分自身を振り返らせる問いかけを使ったりすると、具体的なイメージを抱いてもらいやすくなります。
これらの基本要素を理解してから実践することで、キャッチコピー自体がより戦略的になります。最終的なゴールが集客なのか、知名度アップなのかを定めたら、そのために活かせる方法を取捨選択するとよいでしょう。
人を惹きつけるフレーズの磨き方
「人を惹きつける」フレーズに仕上げるためには、どのように言葉を組み合わせるかも重要です。思いついたコピーを一度書き出し、改善の余地がないかを客観的にチェックしてみましょう。フレーズを磨くには、まず複数のコピー案を書き出し、客観的に見直すことが重要です。実際の使い方を想定しながら、特定の強みを強調する比喩表現や数字、あるいはユーモアを交えられないかを考えることで、読み手にはより強い印象を与えやすくなります。形容詞やオノマトペなどの言葉を使う際には、その響きがターゲットの耳に心地よいか、想像しやすいかを見極めることも大切です。
フレーズづくりの段階では、いくつかの候補を並行して作り、最も説得力が高く、中小企業の独自性をアピールできるものを選ぶことが効果的です。就職活動用の自己紹介であれば、個人の強みを一言でまとめて印象づけるように、たとえば「折れない芯のあるスポンジ」のように、比喩的で印象づけるようなイメージで表現する手法もあります(参照*1)。ビジネスでも、自社の特徴を親しみやすく言い表す工夫があれば、読み手との距離を縮めることができます。
ただし、面白さや親しみを重視しすぎるあまり、伝えたい軸が見えなくなるのは避けたいところです。求めるアクションは問い合わせにつなげることなのか、商品を記憶してもらうことなのか、企業イメージを向上させることなのかなど、最終的な目的をはっきりさせながら、不要なフレーズはそぎ落としましょう。感覚的な言葉だけでは根拠が弱いと感じる場合は、具体的な数字や改善実績などを加えることで説得力を高めることができます。
必要に応じて、販売実績や顧客の声など具体的な根拠を加えると説得力を補えます。
こうした手順を踏むと、限られたリソースの中でも印象に残るフレーズを生み出せます。試行錯誤を繰り返すうちに、少しずつ読み手との共通認識や感情的なつながりを生むコピーづくりのコツが見えてきます。柔軟に発想を切り替えながら、自社やサービスの魅力を最大限に伝える表現を磨いていくことがポイントです。
実践的な成功事例と工夫
キャッチコピーは、実際の事例を見るとさらに理解が深まります。
たとえば、数値をタイトルに盛り込みながら、短く端的にまとめることで信頼感を高める方法があります。具体例として、売り上げを伸ばした店舗が、広告に「この方法で売り上げが2割増に」などの数字を含むコピーを採用し、顧客の興味を強く引きつけたケースがあります(参照*2)。人は数字が加わると「根拠」や「具体性」を想像しやすくなるため、つい気になって読み進めてしまいます。
また、内容を否定形にして興味を引く事例も挙げられます。たとえば「知らなければ損をするポイント」というような言い回しは、読者に注意喚起を促し、何が損につながるのかを確かめたくなる気持ちを誘発します。さらに、比較表現を使い「従来品とどのように違うのか」を示す手法も有効です。中小企業の場合でも、これまで使われていた方法との違いを明示することで、一目でメリットや特徴を把握してもらえるようになります。
キャッチコピーを作成する段階で、読者が得られるメリットを想像してもらう工夫も重要です。具体的なイメージを刺激するために、視覚や感覚に働きかける言葉を混ぜたり、短いフレーズでストーリーを感じさせたりすると、一瞬で心をつかむことができます。大げさな表現になりすぎると逆に疑念を生む可能性もあるため、内容と整合性のある範囲で強調することが大切です。これは特に小規模なビジネスでは、信頼関係を築く上で欠かせない視点です。
最終的に、キャッチコピーはタイトルや広告経由で顧客との初対面をつくる役割を担います。大がかりなプロモーションでなくとも、限られた場所とタイミングで強く訴求できるよう、成功事例に触れながら自社に合った工夫を取り入れることが効果的です。タイトルやフレーズのわずかな違いで反応が大きく変わるため、こまめな検証と改善を重ねていくことがポイントです。
まとめ と小さく始める提案
ここまで見てきたように、「人を惹きつける」キャッチコピーを作る際は、ターゲットを理解し、シンプルで具体的な表現を選び、相手の感情や関心事に訴えかける言葉選びが大切です。限られた文字数であっても、数字や具体例、ビジュアルを想起させる言葉を巧みに組み合わせれば、初めて出会った人の心にもすっと入り込むメッセージを届けることができます。
中小企業は大企業のように広告費を潤沢にかけることが難しい場合が多いですが、だからこそ一つひとつのクリエイティブに注力し、それを有効活用することで効果を高めやすいという強みがあります。小規模ならではのフットワークを生かし、試したコピーをSNSや店頭などですぐに反映し、反応を観察して改善を重ねるというサイクルを回すことが重要です。たとえば、お店の掲示物やオンラインストアの商品名など、今すぐ変えられるところから手を付けてみて、反応の良い言葉をブラッシュアップしていきましょう。
また、コピーを考える段階でハードルを高く設定しすぎる必要はありません。最初から完璧なキャッチコピーを求めるよりも、数案テストしてみて、お客様の反応から「伝わる言葉」を探るほうが現実的です。そこから手ごたえのあるフレーズをさらに洗練し、次のPRツールへと広げていくと、少しずつ成果が積み重なっていきます。
最後に、キャッチコピーは常に「読んだ人がどう思うか」に焦点を当てることが大前提大切です。どんなに商品や企業が魅力にあふれていても、その良さが一瞬で伝わらなければ、多忙な人々の目には留まりません。逆に言えば、人を惹きつける要素を適度な長さで伝える技術を磨いていければ、大きな予算をかけずとも、しっかりと集客につなげる道が開けます。キャッチコピーは小さく試しながら磨いていくという姿勢が、最終的に大きな成果を生む鍵になると考えています。
監修者
小池 正也(こいけ まさや)
Yahoo! JAPANの広告代理店にてWEB広告の運用に携わる。2009年、茨城県での事業立ち上げを機にUターンし、地域に根ざしたWEBマーケティング支援をスタート。これまで300以上の企業や店舗のWEB広告に携わる中で、広告を出すだけでは成果につながらないという課題を実感。
現在はWEBマーケティング全般に携わり、企業の魅力を引き出すWEBサイト制作や、Google広告・Yahoo広告・DSP広告・SNS広告などの運用、Googleアナリティクスを活用したアクセス解析を行う。現場での経験を活かした、改善提案を行っている。
出典