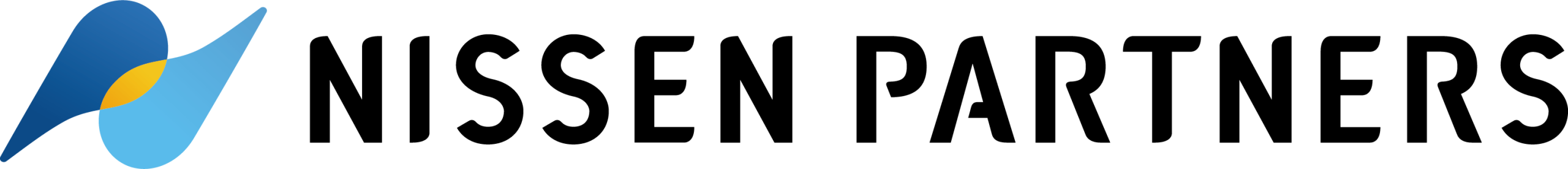はじめに
中小企業が事業を成長させるうえで、マーケティングの強化は重要な取り組みです。外部の代理店やコンサルティング企業に委託する方法もありますが、予算の制約や社内に知識を蓄積したいというニーズから、内製化が注目されています。本記事では、限られたリソースでも実行できる内製化の進め方を、実例や調査結果を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、マーケティングを社内で完結させたい中小企業の経営者が、具体的な準備や社内体制づくりのポイントを把握し、自社に合った方法を模索できるようになることを目指します。
中小企業におけるマーケティング内製化の現状
内製化の割合と社内体制
最近の調査によると、マーケティング業務を外注メインで一部内製化している企業は約4割、内製メインで一部外注が約27%、すべてを内製化している企業は約25%という結果が示されています(参照*1)。社内のマーケティング従事者が1名の場合、約6割が内製化を選択している一方、8名以上になると内製と外注の併用が増える傾向がみられます。外注している業務の上位には「マーケティング施策シミュレーション作成」「コンテンツマーケティング」「コンテンツ制作」などが挙げられ、内製化したい業務も同様の傾向です。
内製化を希望する理由としては、「社内の人的リソースがある」「知見を溜めたい」「外注費用を削減したい」などが多く挙げられています。一方、専任者の採用予定がない、外注予算がある、育成が難しいといった理由で内製化を進めたくない企業も存在します。
中小企業がマーケティングを自社で担うメリットは、施策を素早く実行できることや、企業独自の視点を反映しやすい点です。特に意思決定のプロセスが短い場合、事業部門と密に連携し、状況に応じた施策を即時に展開できます。その結果、外部委託では得られにくい迅速性や柔軟性が確保され、コスト削減以上の価値を生む可能性もあります。
人材不足と外部活用のジレンマ
多くの企業が抱える課題として、人材の不足や専門知識の断絶があります。調査によれば、インハウス化に着手している企業は全体の86%に上るものの、社内担当者のスキル不足や必要な人材の確保が難しいという声が約4割を占めていました(参照*2)。これは、データ解析やデジタルを前提としたマーケティング手法が求められる中、内製化を阻む要因となっています。
外注を利用すれば専門人材の知見を素早く取り入れられるメリットがありますが、すべてをアウトソースすると社内にノウハウがたまりにくくなります。そこで、初期段階で外部パートナーの専門知識を活用しつつ、徐々に内製化するハイブリッド型のアプローチを取る企業が増加しています。こうした段階的な移行は、現実的な予算管理や人材育成を可能にし、日々の業務に支障をきたさない範囲で内製化のメリットを獲得できる点が特徴です。
マーケティングを内製化する具体的プロセス
ステップ1: 目標設定と課題整理
マーケティングの内製化を円滑に進めるには、まず明確な目標設定と課題の洗い出しが必要です。たとえば「新規顧客の獲得数を半年で2倍にする」「既存顧客のリピート率を一定期間で向上させる」といった具体的な指標を定めることで、取り組むべき施策の優先順位を見極めやすくなります。
加えて、自社が抱える制約を整理することも欠かせません。調査ではデジタル人材の不足を感じる中小企業が約53.7%にのぼり、採用に前向きな企業は71.6%存在するものの、最終的な採用決定は約3割にとどまるとの報告があります(参照*3)。こうしたギャップを埋めるには、外部から専門家を呼ぶのか、既存社員を研修するのか、予算と時間の両面で実現可能な方法を検討する必要があります。
ステップ2: 人材とツールの導入
目標と課題が明確になったら、次に取り組むべきは人材確保と業務を支えるツールの導入です。人材確保にあたっては、既存の社員をリスキルして活用する方法や、一定期間だけ外部の専門家を雇用するなどの選択肢があります。特にデジタルマーケティングではツールの操作やデータ解析スキルが重要となるため、最初の段階から連携しやすいメンバーを選ぶことがポイントです。
ツール導入の面では、社内で運用しやすいクラウド型のSNS分析ツールや、顧客情報を一元管理するCRM(顧客関係管理)などの利用が代表的です。費用対効果を検証しやすく、外注に匹敵するレベルの分析や施策立案が可能になります。導入前には機能とコストのバランスを見極め、運用ルールの整備や担当者の教育も意識して進めると良いでしょう。
ステップ3: ハイブリッド体制の構築
内製化を進める中で、あえて外部の専門家と連携しながら自社の知見を強化していく形を、ハイブリッド体制と呼びます。調査でも、インハウス化を進めている企業の約63%が戦略設計や運用まで幅広く外部パートナーを活用していることが分かっています(参照*2)。これにより、最新の技術やノウハウを学びながら、社内にナレッジを蓄積できます。
予算を抑えて結果を出す実践例
SNS運用の内製化
近年ではSNSを活用した集客やブランド認知の向上が重要になっています。しかし、日々の投稿や反応分析をすべて手作業で行うのは工数がかかりすぎます。そのため、SNS分析ツールの導入が効果的です。たとえば、Instagram InsightsやXアナリティクスといった無料ツールから始めることで、投稿のエンゲージメントやフォロワー属性を可視化し、施策の改善につなげられるようにします(参照*4)。
さらに、SocialDogやHootsuiteといった有料ツールを導入すれば、複数SNSの一元管理や高度な分析、レポートの自動生成などが可能となり、運用効率が大きく向上します。無料ツールから段階的に移行することで、最小限の投資で効果を見極めつつ、徐々に本格的な運用体制を構築できます。注意点としては、社内の利用者全員がツールの使い方を理解し、レポートを読み解くための基礎知識を身につけることが大切です。
DX活用による効率化
SNS以外にも、デジタル技術を活用することで業務効率と成果を同時に高める事例が増えています。たとえば、金型内製化や自動加工機を導入して一貫生産体制を確立したり、ITシステムを使ったりして在庫管理や生産ラインを効率化する中小企業の事例が報告されています(参照*5)。こうしたものづくりの領域だけでなく、農業機械や食品まで幅広い分野にわたり、データ活用による新たな価値創出が進んでいるのも特徴です。
また、経理データとマーケティングデータを連携させ、費用対効果を明確に把握することも重要です。会計ソフトを活用して資金繰りと広告投資を同時に管理すれば、費用の削減と売上拡大を両立しやすくなります(参照*6)。社内で定期的にデータを共有し、投資すべき分野と削減すべき項目の優先度を明確にすることが、コストを抑えながら目に見える結果を出す近道となります。
おわりに
本記事では、中小企業がマーケティングを内製化する際の現状や課題、そして実践的なプロセスと具体例を整理しました。限られた人材や予算でも、目標を定め、段階的な体制構築を進めることで、外注に依存しすぎない柔軟なマーケティング活動が可能になります。社内に蓄積された知見をベースに、より的確な戦略をリアルタイムで実行できる点こそ、内製化の大きなメリットといえるでしょう。
すべてを一度に内製化しようとすると、コストや人材負担が大きくなることもあります。そのため、最初は外部パートナーとの協働を検討しながら、少しずつ社内でカバーできる領域を広げていくのも現実的な方法です。こうした柔軟な姿勢で、企業規模や市場環境に左右されない強い経営基盤を築くことができます。本記事が、今後のマーケティング活動の参考となれば幸いです。
監修者
小池 正也(こいけ まさや)
Yahoo! JAPANの広告代理店にてWEB広告の運用に携わる。2009年、茨城県での事業立ち上げを機にUターンし、地域に根ざしたWEBマーケティング支援をスタート。これまで300以上の企業や店舗のWEB広告に携わる中で、広告を出すだけでは成果につながらないという課題を実感。
現在はWEBマーケティング全般に携わり、企業の魅力を引き出すWEBサイト制作や、Google広告・Yahoo広告・DSP広告・SNS広告などの運用、Googleアナリティクスを活用したアクセス解析を行う。現場での経験を活かした、改善提案を行っている。
出典
- (*1) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – マーケティング業務の内製(インハウス)化に関する調査|2023年11月実施
- (*2) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – インハウス化着手企業は86%!課題は「スキル不足」「人材確保」
- (*3) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 〈中小企業とデジタル人材に関する実態調査〉デジタル人材を必要としている企業は75.0%53.7%の企業はデジタル人材が社内にいないという現状中小企業のデジタル人材活用は進んでいない実態が明らかに
- (*4) マーケティング内製化支援メディア – あなたの会社にマーケターを – 【2025年最新】SNS分析ツール完全解説!中小企業でも成果が出る選び方と活用法
- (*5) 中小企業研究センター – 2024年度表彰企業のご紹介
- (*6) 株式会社アカウンティングストラテジー – 経営、経理、マーケティングの連携がもたらす、中小企業の成長戦略